やっかいな雨漏り
工事部の保坂です。
先日、法人様より自社所有の建物の雨漏りのご相談があり今回は雨漏りについてお話しさせていただきます。
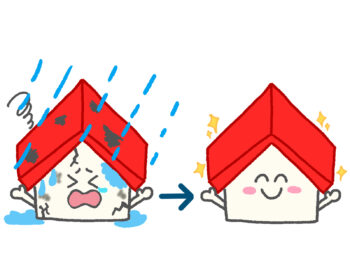
近年は集中豪雨、暴風雨、台風、竜巻といずれも威力が増しているように感じております。
私たちは屋外作業が多いのですが、数年前から6月から猛暑が始まるように感じていて、今年は終わるのも遅かったです。
そして今までには無かったような悪天候も起きるようになり、これまで雨漏りをしなかった建物にも被害が出てきてしまう状態になっているように感じています。
屋根、外壁やサッシ等、外気に面する部分へ雨水が触れて何らかの要因で室内に侵入するわけですが、雨漏りの原因は多種多様です。
経年劣化、創意工夫を加えた造り方で施工したものの雨仕舞不足であった場合はピンポイントでの調査で対応策がつかめてくることが多いです。
もう一つのケースとしては近年の悪天候による雨漏りの場合。
どのような建物を建てるにしても、雨漏りが生じないようどこの会社でも注意や検討を重ねて造られているでしょう。
屋根、笠木、庇、外壁、サッシ周囲、バルコニー等の施工では、漏水しないよう各々の工種毎に従来より雨仕舞を考慮した納め方で施されているので、室内へ雨水が侵入しないはずなのです。
それなのに雨漏りしてしまう。
原因を探るために、雨漏り現場の目視と散水試験を重ねています。
散水しても室内から漏水が無い場合は、漏水部の造られ方を図示し、悪天候時を想定して雨水の侵入経路を考えます。
例をあげますと、屋根、外壁等、どの部位についても従来からの建築的な納め方で雨水が侵入した場合には排水される仕組みがあるのですが、その部位から逆流する環境になってしまった時の雨漏りです。
本来は排水する為の仕組みなので、効果と意味のある必要な造りなのですが、暴風雨等で室内外の気圧差が生じた時等に、外気を内気に吸引するような状態になり、外気と共に雨水も引き込んでしまうのです。
実際に我が家でも同じような状況を目で見て体感した経験があります!
また集中豪雨の際は同じような意味合いの部位に長時間、雨水に触れることで表面張力作用の連続で室内に通じてしまうケースです。
調査で気付けた事例では対応装置方法に繋がっていくのですが、そもそも雨漏りしないよう造られているのに漏水してしまった事態を改善していこうとするので、なかなか難がある内容ではあります。
このようにDAISHUでは経験値を重ねた工事部員が、何とか改善していこうと踏み込んだ検討も行っています。
新築、リフォーム、修理や改善等、建築工事全般のご対応が可能でございますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
▼他の工事ブログはこちら▼
工事ブログ | 市川市の工務店DAISHU







